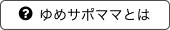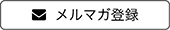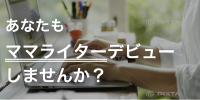習い事・しつけ
なんで嫌いなの? 子供の好き嫌いは食べることだけじゃなかった?!
<子供の好き嫌いに悩んだことはありませんか?>
子育てするようになって初めて食べ物に対する見方が変わりました。
うちの子は1歳になる前から好き嫌いがとても多く、特に葉物系の野菜が食べられません。
「離乳食の食べさせ方がいけなかったのかな…」
「私の料理の仕方がダメなのかな…」
そんなことを悩む毎日でした。
それでも「ママが諦めたらいけないんだ!」と思い、形を変えたり、味付けを変えたりしながら挑戦する毎日。
・・でもやっぱり食べてくれません。

そんな時に「好き嫌いは口の中だけの問題ではない!」というお話しを聞きました。
食べるということは、口の中をたくさん刺激し、舌や歯を使っているということ。
そして感覚が過敏な子は、初めての触感にも敏感に反応して嫌がってしまうということ。
なるほど!!
うちの子も感覚が敏感で嫌がっているのかもしれない!
まずは指で色んな感覚を味わってもらうようにしました。
炊く前のお米のようなバラバラした物、粘土のような柔らかいもの、なんでも触ってー!という気持ちで。
今では、相変わらずの野菜嫌いですが、今度は緑色の物が苦手だったりと色に限定されてきました。
また育児の挑戦です。
子供はまだ初めてのことだらけですもんね。
「急に何かをできるわけではない」と分かっていても、
親は「やって欲しい」という気持ちが強く、つい焦ってしまいます。
特にずっと一緒にいるママなら、なおさら。
「食べない」ということがストレスになっていましたが、
食べることだけに執着するのでなく、物事を考えるようにしたら、
案外スッキリしました。
育児って本当に悩む毎日です。
それでも楽しい毎日。
子供がいるからこそ感じる毎日です。
ペンネーム:ぴいちゃん
子育てするようになって初めて食べ物に対する見方が変わりました。
うちの子は1歳になる前から好き嫌いがとても多く、特に葉物系の野菜が食べられません。
「離乳食の食べさせ方がいけなかったのかな…」
「私の料理の仕方がダメなのかな…」
そんなことを悩む毎日でした。
それでも「ママが諦めたらいけないんだ!」と思い、形を変えたり、味付けを変えたりしながら挑戦する毎日。
・・でもやっぱり食べてくれません。

そんな時に「好き嫌いは口の中だけの問題ではない!」というお話しを聞きました。
食べるということは、口の中をたくさん刺激し、舌や歯を使っているということ。
そして感覚が過敏な子は、初めての触感にも敏感に反応して嫌がってしまうということ。
なるほど!!
うちの子も感覚が敏感で嫌がっているのかもしれない!
まずは指で色んな感覚を味わってもらうようにしました。
炊く前のお米のようなバラバラした物、粘土のような柔らかいもの、なんでも触ってー!という気持ちで。
今では、相変わらずの野菜嫌いですが、今度は緑色の物が苦手だったりと色に限定されてきました。
また育児の挑戦です。
子供はまだ初めてのことだらけですもんね。
「急に何かをできるわけではない」と分かっていても、
親は「やって欲しい」という気持ちが強く、つい焦ってしまいます。
特にずっと一緒にいるママなら、なおさら。
「食べない」ということがストレスになっていましたが、
食べることだけに執着するのでなく、物事を考えるようにしたら、
案外スッキリしました。
育児って本当に悩む毎日です。
それでも楽しい毎日。
子供がいるからこそ感じる毎日です。
ペンネーム:ぴいちゃん

習い事・しつけ
子どもの家事参加いつからがベスト!?
お家での役割は、健やかな成長につながる♪
子どもが家事に興味を持ったら・・・お手伝いのチャンス!
お手伝いからスタートして、家事を担うようになると
家庭内での居場所につながるそうです。

やらないと、誰かが困ることをチョイス
家事の「手伝い」の段階では
あくまでも、大人の補助。
場合によっては、補助にもならないかもしれません。
そんな時は、ママには忍耐が必要かもしれませんが
そこは、成長過程の一つですから、ちょっと我慢。
お手伝いをする時は、「それをさぼると他の誰かが困る」
というものがオススメです。
例えば・・・
・お風呂掃除
・炊飯
・布団の上げ下ろし
・洗濯
・料理
などです。
逆に、
・朝、新聞をとってくる
・玄関の掃き掃除
・洗濯をたたむ
などは、もしかしたらやらなくてもなんとなく生活できてしまうかもしれません。
この
「自分がやらないと、他の人が困る」
ことがポイントです☆
年齢に応じて、できることとできないことがありますが
ぜひ、このポイントを第一にして何をやるか決めてくださいね。
もちろん、親から一方的にではなく、子どもと相談してです。
何歳から?
何歳から、家事の手伝いはできるでしょうか。
手伝いがいつしか、そのまま分担になるためには、早い方が良いと思います。
ちなみに、我が家の場合は、年中さんの夏休みからです。
夏休みに、「お手伝い」という宿題みたいなものが出ますよね。
その時がチャンスです☆
最初の「やらないと誰かが困ること」をポイントに
お手伝いを決めます。
できれば長く続けられそうなものがいいですね(^^)
そして、次に書く「褒める!感謝する!」で
子どもに気持ち良くなってもらいましょう。
褒める!!感謝する!!
あくまでも、長期休みのお手伝いで始めたとしても
そのまま継続するには、コツがあります。
まず、休み中から
褒めまくる!
感謝しまくる!
例え、
綺麗にできなくても・・・
早く出な聞くても・・・
決して怒らない。
できたことを褒める!
そして、家族みんなが感謝する!
子どもが大人から本気で感謝される体験って
日常生活の中であまりないから
すごく嬉しい体験になるはずです。
その体験が、子どもの成長にも役立つと思います。
そして、長期休みの終わりに・・・
とても、助かったこと、嬉しかったことなどを伝え
「これからも、やってくれるとママとっても嬉しいし助かるな〜」
なんて、伝えてみてください。
我が家は、この流れで年中さんの夏休みから
かれこれ13年(笑)
米とぎに関しては・・・もう、主婦の私よりプロです。
息子も、米とぎには自信を持っています。
そして、本当に彼の炊くご飯は美味しい♪
本当に役立つのは思春期
家事分担は、ママが楽になるからという理由ではありません。
実は、思春期・・・
口もろくにきかなくなる時期でも
子どもの「居場所」になるのです。
ハード面ではなく、ソフト面で。
「お風呂お願いしまーす」
「いれたよ」
「ありがとう」
こんな何気ない会話でも・・・
反抗期には、重要です(笑)
仮に、諸事情で他の人がやった時は
「あ、ありがと」
と、自分の役割だと思っているため素直に言うことができます。
このことは、中学生の時、担任の先生からも随分褒めていただきました。
実際に、彼の「役割」があることで
どんな時でも、家族は感謝しあえたと思います。
我が家での体験から、家事分担の始まりはお手伝いから。
そして、できるだけ小さいうちから取り組むのがオススメです。
自分がやった方が早いからと、役割を取り上げないこと。
ここだけは、ママの辛抱です・・・(^_^;)
でも、辛抱してでも、この家事分担はトライする価値があます。
子どもたちは、どう思っているかわかりませんが・・・
大学生と高校生の息子を持つ親として今振り返っても
これは、ぜひみなさんにオススメしたいと思う良い取り組みだったと思います。

この記事を書いた人 大口 知子

フリーライター・簡単レシピ研究家
夫、大学生・高校生の息子二人
ゆめサポママ@ながの代表メンバーの一人。文章を書く仕事の傍ら、ブログに掲載していた手抜きに見えない手抜きレシピがきっかけでTV出演することに。
SBCテレビ「3時は!ららら♪」NHK長野放送局「ひるとく」などを経て、現在テレビ信州「ゆうがたGet!」木曜レギュラー出演中。
本業ではライティングスクールで後輩の指導にも注力。
http://pianpiano.naganoblog.jp

習い事・しつけ
なぜ、食事をするの?(その2)
キッズ野菜ソムリエの育成・活動から
皆さん、こんにちは!野菜ソムリエの増田朱美です。
前回はキッズ野菜ソムリエについてお話しました。
今日は、今の子どもたちの様子から、子どもの食、野菜・果物を主にお話いたします。

空にはトンボも飛び交い秋がそこまできていますが今年の夏も暑かったですね。
住んでいるまわりには家庭菜園をされている方も多く、
夏の野菜、きゅうり・なす・トマト等を「おすそわけ」でたくさんいただくことも多いと思われます。
毎日同じ食材だと
「え~、またきゅうりぃぃぃぃ」
というブーイングも子どもはついつい発しているようです。
何を隠そう、私自身もその昔は通った道でした。しかし我が母は「嫌なら食べなくていい!」と。
自分で料理ができなかったので素直(?)に食べていました。
今では、自身が親となり、また健康等を考えることが多くなり、
その環境にあったことを感謝している日々です。
まず、そんなブーイングにも屈せず(笑)、夏には夏に旬の、
秋には秋に旬を迎える野菜・果物を食べることをおすすめします。
その時期に収穫できるものは、私達にとっても必要としている栄養・機能がたくさん!
毎日同じ野菜等は当たり前。
我が子が親になって、それがわかってくれる時がくると信じ、
反発されても旬の野菜・果物を毎日続いても、調理しましょう!
また料理は簡単なもので大丈夫!
旬のものは手をかけなくてもそのものがもつ美味しさがぎっしり詰まっています。
かぼちゃは蒸しただけでも十分甘さを感じます。
大根もおだしでコトコト煮含めるだけで甘さも出て美味しい!
このくらいの料理なら子どもでもできますね。
その昔は子どもも家庭の仕事をしっかり担当していたものです。
フルタイムで働き、疲れた中食事を作るのもちょっぴり負担が・・・。
でも、旬の野菜・果物はそれ自身がもつ美味しさで簡単調理でも最上級の美味しさになります。
子どもの食事のお手伝いといっても、包丁の扱い等は心配なもの。
手伝ってもらいたいし、料理も覚えてもらいたいけど、家ではけんかになっちゃう・・・
そんなことが続くと子どもはもう手伝うとは言わなくなる・・・悪循環。
そういう時は、私どもNPO法人食育体験教室コラボでも開催しています、
子ども向けの料理教室等に参加をおすすめします。
子どもも自分のやる気が満足し、また親もキラキラ輝いた目をしながら参加する子どもの様子を
一歩下がってゆったりした気持ちで寄り添える。とてもよい機会です。
ぜひ、お母さん、アンテナをめぐらし子供向け料理教室を探してあげてくださいませ!
そうやって子どもが自分で料理ができるようになると、野菜・果物にも興味が湧くでしょう。
次第に、「ごはんを食べることは生きるため」に気がつき、
「自分の身体は食べ物でできている」も、理解できるようになるでしょう。
更に、それが「腑に落ち」しっかりと自分の意識に入ってくれると思います。
私自身、「自分の身体は食べ物でできている」が腑に落ちたのは、
数年前のあること(ここでは割愛します)がきっかけでした。
随分遅かったこととても悔いが残ります。もう少し早く気が付きたかった・・・。
ですので、私の経験からも、子どものうちから、
「旬の食べ物を食べる意味」
「自分の身体は食べ物からできている」
これらを無意識の中にも、日々の食事をしながら、
その子の理解度に合わせたお話を皆さんから子どもへお話していただきたければ、
きっと子どもは、更に毎日笑顔で元気に過ごしてくれるでしょう。
2回にわたり、野菜ソムリエとして皆さんにお伝えしたいことお話いたしました。
どうもありがとうございました。

この記事を書いた人 増田 朱美

・日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエ(アクティブ)
・日本野菜ソムリエ協会認定 キッズ野菜ソムリエ認定講師
長野県中野市在住。
りんご兼業農家に育ち、 野菜・果物に囲まれた食生活を送る。
資格取得後、野菜ソムリエを活かし転職。
料理コンクール4回優勝を重ね、レシピ開発、料理教室講師を中心に活動中。
(SBC信越放送「3時は!ららら♪」笑顔の食卓レギュラー出演(約2年間)。
「ヨークカルチャー「体調を整える 野菜・果物の食べ方」講師、週間長野「野菜のおはなし」連載中。」
ブログ:http://nekomin.naganoblog.jp/

習い事・しつけ
なぜ、食事をするの?(その1)
キッズ野菜ソムリエの育成・活動から
皆さん、こんにちは!野菜ソムリエの増田朱美です。
野菜ソムリエの資格を取得してもうじき10年。
我が子も既に成人し、少しだけ(←いえいえ、たくさん?笑)子育ての道を先に行く先輩として、
また野菜ソムリエの活動を通して感じたこと等、2回にわたりお話いたします。

「キッズ野菜ソムリエ」はご存知ですか?
そう、野菜ソムリエの子ども版!(野菜ソムリエの説明は又の機会に・・・)
キッズ野菜ソムリエのお仕事は2つ。
①野菜・果物を楽しむこと
②お友達に野菜・果物の魅力を伝えられること
つまり、子どもから子どもへ伝える食育の新しい形です。
このキッズ野菜ソムリエになるには任命イベントに参加してもらいます。
現在私はこの講師と同時に、イベントそのものを長野県内で最も多く開催している、
NPO法人食育体験教室コラボ(略:コラボ)の理事もしています。
理事長の飯島美香さんとの出会いから、県内に80名程のキッズ野菜ソムリエが誕生しています。
キッズ野菜ソムリエになるために、まず3種類のトマトの食べ比べを体験。
見ため・香り・味・食感をそれぞれ自分の言葉で表現します。
「実はトマト嫌い、食べられない」という子ども達も、
隣の子どもの姿を目の当たりにして、
ちゃんと食べてしっかり表現できるのです!
その時の「嫌いなのに食べることができた!」という気持ちは、自信に変わり、
また、その子どもだけに限らず会場の雰囲気も素晴らしいものへと激変。
どの子も、キラキラした目の輝き、おもいっきりの笑顔となります。
その笑顔が頂点に達するのは、認定証を渡した後に、
キッズ野菜ソムリエエプロン&黄色のチーフを着用した時!
この笑顔を見ることを楽しみに、キッズ野菜ソムリエ認定講師をしている私です。
今の世の中、とても目まぐるしく、時間の流れがとても早いと感じます。
子育て真っ最中のお母さん、昼間はフルタイムで仕事。夜は家のこと・・・
と自分の時間が取りづらい毎日ですよね。
そんな中でも、子どもの成長にとって重要である食事のこともしっかり対応。
お母さんはいつも頑張っています!
コラボでは今年、主にキッズ野菜ソムリエの子どもたちのために、
農作業体験・料理教室、イベント出演等を行っています。
農作業体験はじゃがいも!肥料づくりから始まり、植付け、収穫。
今度は大豆収穫も!料理教室では伝統料理も作りました。
そして、自分たちが主役の野菜の日のイベントも体験!
これらの開催情報は、先の頑張っているお母さんにきちんと届き、
子どもたちも、お母さん、更にはお父さんも笑顔いっぱいで参加。
小さい頃から、また家族みんなで食べ物のことに関心を持ってもらえる
良い場になっている様子に、私達関係者はいつも嬉しく思っています。
まだまだ、キッズ野菜ソムリエの活動の様子等詳しくお話したいのですが、今回は、このくらいに・・・。
次回は、野菜ソムリエとしての視点から、働くお母さんに向けて、具体的なメッセージをお伝えいたします。

この記事を書いた人 増田 朱美

・日本野菜ソムリエ協会認定 野菜ソムリエ(アクティブ)
・日本野菜ソムリエ協会認定 キッズ野菜ソムリエ認定講師
長野県中野市在住。
りんご兼業農家に育ち、 野菜・果物に囲まれた食生活を送る。
資格取得後、野菜ソムリエを活かし転職。
料理コンクール4回優勝を重ね、レシピ開発、料理教室講師を中心に活動中。
(SBC信越放送「3時は!ららら♪」笑顔の食卓レギュラー出演(約2年間)。
「ヨークカルチャー「体調を整える 野菜・果物の食べ方」講師、週間長野「野菜のおはなし」連載中。」
ブログ:http://nekomin.naganoblog.jp/

習い事・しつけ
幼稚園に入園して食べられなかったもの…その1
まさかの・・・食べ方を知らない・・・
我が家の上の子、3歳で幼稚園に入園しました。
その時、食べられなかったもの・・・それは・・・
みかん・・・
嫌いだったわけではありません。
皮をむけなかったのです(^_^;)
今となっては笑い話ですが、なぜ、むけなかったのか・・・
そんな我が家の子どもたちのエピソードシリーズです☆

先生からの予期せぬ質問
上の子が生まれてじきに転勤で見知らぬ土地へ行った我が家。
その町で幼稚園に入園しました。
ある日、幼稚園へ迎えに行ったら、担任の先生に聞かれました。
先生「お母さん、◯◯くん(うちの息子)は、みかんを食べたことがないのですか?」
へ???
予期せぬ質問に一瞬固まったものの・・・
私「いいえ。食べたことは、あります。」
先生「じゃあ、自分でむいたことはないですか?」
この質問に、再度、固まりました・・・
え????????????????
しばし、沈黙していたら・・・
先生「今日、お昼にみかんが出たのですが、◯◯くんが食べないので、みかんも食べてと言ったら、丸ごと食べようとしたのです。」
私「・・・・・・」
先生「それで、びっくりして私が半分に割ってあげたら、今度は半分ごと食べようとしたのです。」
私「・・・・・・・・・・・・・」
先生「だから、もしかして、自分でみかんを剥いたことがないのかと思って・・・」
私「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・絶句」
もう、その時、何と答えたかも覚えていません(笑)
ええ。そうでした。たぶん。
うちの長男、自力でみかんをむいたことがなかった(笑)
おぼっちゃま!?
テーブルに座って、自分の前に一房ずつ並べられたみかんしか食べたことがなかった(爆)
どんだけ、おぼっちゃま育ちーーーーーーーーーーーー
おぼっちゃまでもないのにーーーーーーーーーーーーーーーー(笑)
生まれてから、とにかく食が細くて、ミルクも離乳食もあまり進まなかった。
だから、あの手この手で食べさせようとした。
追いかけてまで食べさせたりはしなかったけれど
食べる時間には、食べることに興味をもってもらいたくて
一所懸命だった・・・
でも、後になってわかった
別にその時食べなくても良かったんだって(笑)
見知らぬ土地で、知り合いも、友達も、親もいない、
頼れる人もいない、そんな土地で初めての子育てをしました。
当時は、まだインターネットも普及していなくて
情報は、まだ流行り始めの育児情報誌だけだった。
そこに書かれているように・・とまでは思わなかったけれど
せめて、三度の食事とか睡眠とかリズムよく生活できるように・・・
そんなことを考えていたのは事実だったと思う・・振り返ってみれば。
良くも悪くも、専業主婦だったから手もあったんだな・・・
やりすぎたね(笑)
自分では過保護のつもりはなかったけれど・・・
きっと、過保護だった。
上の息子は特に(^_^;)
とはいえ・・・
そんな食の細かった息子も、高校生の時には、お昼のお弁当の他に部活前に食べるおにぎりを持って行ったくらい、食欲旺盛になりましたし、今では東京で一人暮らしをしています。
育つもんです(*≧艸≦)
もちろん、自分でみかんも食べられます(笑)(笑)(笑)
そして、反面教師とでも言いましょうか
このエピソードを踏まえた、二人目の子育てでは・・・
自分からみかんを食べようとした時は、たとえぐちゃぐちゃになろうと
母、ぐっとこらえました(笑)
これだったんだなあ(笑)
まあ、もともと、食に興味があるかないかは、同じ親から生まれても違うわけだし
その辺りも影響するとは思うけれど・・・
仮に、食が細くても、標準体重があれば気にしなくていいってこと(*≧艸≦)
少しずつ自分でできるようになることが大切って話です(^^)
さて・・・
幼稚園に入園して食べられなかったものは、まだありました(笑)
それはまた次回・・・

この記事を書いた人 大口 知子

フリーライター・簡単レシピ研究家
夫、大学生・高校生の息子二人
ゆめサポママ@ながの代表メンバーの一人。文章を書く仕事の傍ら、ブログに掲載していた手抜きに見えない手抜きレシピがきっかけでTV出演することに。
SBCテレビ「3時は!ららら♪」NHK長野放送局「ひるとく」などを経て、現在テレビ信州「ゆうがたGet!」木曜レギュラー出演中。
本業ではライティングスクールで後輩の指導にも注力。
http://pianpiano.naganoblog.jp

習い事・しつけ
子どものチカラ・親のチカラをひき出す
自己肯定感・生きる力の大切さに気づこう
そらいろのたねは、子どもの自己肯定感・生きる力をキーワードに、
子ども向け講座や親育ち講座を開催しているNPO団体です。
子どもたちが自分らしい人生を選び取っていくために、
生きる力として必須の力が身につく講座を提供しています。。

子ども向け講座
◇ことばキャンプ
話を聞く力・伝える力・発表する力を、
ゲーム形式で楽しくトレーニングする月1回のワークショップ。
コミュニケーション力は、
「自然に身につく」とか「性格次第だから仕方ない」と思われがちですが、
トレーニングするれば誰でも身につけられます。
米国の学校でのコミュニケーション力の授業をもとに考案された
グループレッスン形式のプログラムです。
こんな方におススメ
「落ち着いて話をきけるようになれたら・・・」
「人前で話すのが苦手」
「筋道をたてて話せるようになりたい」
ゲーム形式の繰り返し練習により「小さな成功体験」を積み、スキルと自信を育むログラムです。
姉妹団体「ことばキャンプ長野」が、長野・松本塩尻・岡谷で毎月開催中。
(詳細は、ことばキャンプ長野で検索)
◇気持ちのワークショップ
自分の感情とうまく付き合うための講座。
怒りなどの自分の感情に向き合い、どう表現するかを学ぶワークショップです。

親育ち講座
◇家庭での性教育
子どもは3歳頃から「ぼくはどこから来たの?」など素朴な疑問を投げかけてきます。
本来すばらしい仕組みである「性 」のことを、家庭でどう教えるかを提案しています。
◇子育てスキル講座 どならない子育て
子育て方法は、教わる機会もないため、自己流で試行錯誤する方が大半ではないでしょうか。
子どもへの効果的な声掛けを知り、子育てストレスを減らして子育てを楽しみましょう。
ご要望があれば出張講座も承ります。
開催スケジュールなどは「そらいろのたね 松本」で検索してくださいね。
問合せ先 そらいろのたね
ホームページ http://kotobacamp.jimdo.com/
ブログ http://soratane.naganoblog.jp/
メールアドレス sora.tane3@gmail.com
電話番号 050-3634-5939

習い事・しつけ
英語をはじめるなら小さいうち、の実態は?
耳が育つタイミングで、英語教育を取り入れるといい。
そんな話、聞いたことはありませんか?
我が家は、娘が2歳から4歳までの2年間、英語教室に通っていました。
その時の体験談です。

漠然と、何かやらせてあげられたらと思っていた私と夫。
1歳半を過ぎても人見知りが激しい娘だったので、幼稚園入園前に
大人や他の子と関わる機会を増やしたい、そんな思いもありました。
英語、リトミック、ピアノ、水泳、ダンス。
調べてみると、住んでいる地域でも色々な教室があってびっくり。
体験に行ってみようかな、と考えていた時、
たまたま行ったショッピングモールで、
まさに体験会募集イベントをしていたのが、そこの英語教室でした。
全体的な雰囲気と、そして実際にオーストラリア人の先生がいたこと、
娘が「楽しそう!」と言ったこと、色々が重なり、体験レッスンへの参加を決めました。
体験と言っても、実際のレッスンに参加してみましょう♪
という感じだったので、
体験の方が1組と、すでに通っている方が2組の中レッスンがスタート。
歌を歌ったり、カードやパネルを使ったり。
初めは固まっていた娘でしたが、
最後には先生とハイタッチできるまでに慣れていたのが驚きでした。
特に気になる点もなく、娘も楽しそうだしここにしよう、と入会を決め、申し込み。
初めに揃える塗り絵やバッグ、カード、お人形など手続きがあり、お願いをしてその日は帰宅しました。
行くと「Good morning!」で始まるレッスン。
先生が日本語を話すことは、ほぼありません。
挨拶の歌、お天気の歌、体を動かしたり手遊びをしたり。
月ごとにテーマがあり、それに沿ってちょっとお勉強したり、
工作やゲームの時間もありました。
先生の後について発音し、ゲームで簡単なやり取りを繰り返すうち、
あっという間に口から英語が飛び出してくるんです。
子供の吸収力ってすごいんだなあと、目の当たりにした瞬間でした。
一番衝撃だったのは、市のハロウィンイベントに参加した時です。
「トリックオアトリート!」ハロウィンでは定番のセリフのこれ。
レッスンで先生が言うと、ちょっと違って聞こえて、娘は、「ティックアティート」と覚えていたんです。
イベント当日、お菓子をもらった後で、
「トリックオアトリートって、ティックアティートのこと?なんかちがーう!」
と一言。
聞いたままを覚える、単語の概念がないからこそ、
一つの文として、すんなりと吸収出来るんだなと感じました。

幼稚園入園を機に、忙しくなるよりお友達といっぱい遊んでほしい、
そんな願いもあって、教室は辞めてしまった我が家。
しかし、娘の口からは、今も英語の歌や会話が出てきます。
吹き替えなしの英語のままDVDを見る事も好きで、
たまにセリフを真似している場面も見られます。
実際に、「学力」とか、「将来のため」とか、その辺りはわかりませんが、
英語というものを抵抗なく受け入れられること、
海外のものに楽しんで関われること、これは英語教室のおかげかなと感じています。

この記事を書いた人 間藤 まりの

松本市出身上田市在住・男女二児の母。
ベビーマッサージインストラクター。『子育て中』自分も家族も大切に、もっと笑顔の輪が広がりますように。そんな思いで、各種イベントや講座を企画しています。2016年春からは、ライターとしても活動スタート。Webコラム執筆や、思いを言葉にするお手伝いなど。文字を使って伝えます。
https://twitter.com/kirakira_prism8
 お知らせ
お知らせ
*上田創造館・パナホーム東海上田展示場にて
毎月ベビーマッサージレッスン開催中
*市民プラザゆう(上田市)にて
ほっと一息・産前産後のケア講座開催(9月~3月・月1、2回)
*あなたの考えまとめます
インタビュー・ライティング・チラシ制作の請負などモニター実施中
 イベント
イベント
10月15日 パパママフェスタ byぺルメルベーベ
(11月 さとのわマルシェby真田ゆめぐるproject. 計画中)
そんな話、聞いたことはありませんか?
我が家は、娘が2歳から4歳までの2年間、英語教室に通っていました。
その時の体験談です。

英語教室に?
漠然と、何かやらせてあげられたらと思っていた私と夫。
1歳半を過ぎても人見知りが激しい娘だったので、幼稚園入園前に
大人や他の子と関わる機会を増やしたい、そんな思いもありました。
英語、リトミック、ピアノ、水泳、ダンス。
調べてみると、住んでいる地域でも色々な教室があってびっくり。
体験に行ってみようかな、と考えていた時、
たまたま行ったショッピングモールで、
まさに体験会募集イベントをしていたのが、そこの英語教室でした。
全体的な雰囲気と、そして実際にオーストラリア人の先生がいたこと、
娘が「楽しそう!」と言ったこと、色々が重なり、体験レッスンへの参加を決めました。
体験レッスンと入会
体験と言っても、実際のレッスンに参加してみましょう♪
という感じだったので、
体験の方が1組と、すでに通っている方が2組の中レッスンがスタート。
歌を歌ったり、カードやパネルを使ったり。
初めは固まっていた娘でしたが、
最後には先生とハイタッチできるまでに慣れていたのが驚きでした。
特に気になる点もなく、娘も楽しそうだしここにしよう、と入会を決め、申し込み。
初めに揃える塗り絵やバッグ、カード、お人形など手続きがあり、お願いをしてその日は帰宅しました。
実際に通ってみて
行くと「Good morning!」で始まるレッスン。
先生が日本語を話すことは、ほぼありません。
挨拶の歌、お天気の歌、体を動かしたり手遊びをしたり。
月ごとにテーマがあり、それに沿ってちょっとお勉強したり、
工作やゲームの時間もありました。
先生の後について発音し、ゲームで簡単なやり取りを繰り返すうち、
あっという間に口から英語が飛び出してくるんです。
子供の吸収力ってすごいんだなあと、目の当たりにした瞬間でした。
一番衝撃だったのは、市のハロウィンイベントに参加した時です。
「トリックオアトリート!」ハロウィンでは定番のセリフのこれ。
レッスンで先生が言うと、ちょっと違って聞こえて、娘は、「ティックアティート」と覚えていたんです。
イベント当日、お菓子をもらった後で、
「トリックオアトリートって、ティックアティートのこと?なんかちがーう!」
と一言。
聞いたままを覚える、単語の概念がないからこそ、
一つの文として、すんなりと吸収出来るんだなと感じました。

やめるタイミングは・・・
幼稚園入園を機に、忙しくなるよりお友達といっぱい遊んでほしい、
そんな願いもあって、教室は辞めてしまった我が家。
しかし、娘の口からは、今も英語の歌や会話が出てきます。
吹き替えなしの英語のままDVDを見る事も好きで、
たまにセリフを真似している場面も見られます。
実際に、「学力」とか、「将来のため」とか、その辺りはわかりませんが、
英語というものを抵抗なく受け入れられること、
海外のものに楽しんで関われること、これは英語教室のおかげかなと感じています。

この記事を書いた人 間藤 まりの

松本市出身上田市在住・男女二児の母。
ベビーマッサージインストラクター。『子育て中』自分も家族も大切に、もっと笑顔の輪が広がりますように。そんな思いで、各種イベントや講座を企画しています。2016年春からは、ライターとしても活動スタート。Webコラム執筆や、思いを言葉にするお手伝いなど。文字を使って伝えます。
https://twitter.com/kirakira_prism8
 お知らせ
お知らせ*上田創造館・パナホーム東海上田展示場にて
毎月ベビーマッサージレッスン開催中
*市民プラザゆう(上田市)にて
ほっと一息・産前産後のケア講座開催(9月~3月・月1、2回)
*あなたの考えまとめます
インタビュー・ライティング・チラシ制作の請負などモニター実施中
 イベント
イベント10月15日 パパママフェスタ byぺルメルベーベ
(11月 さとのわマルシェby真田ゆめぐるproject. 計画中)
習い事・しつけ
子どもとゲームの付き合い方1〜子どもがほしいソフトの中身を見よう〜
ゲームのルールは時間ばかりじゃない
ゲーム機が各家庭にあるようになって、どのくらい経つでしょうか。
早ければ、園児や小学校低学年くらいでも持っているというご家庭も少なくないと思います。
「機械に弱いから、そういうことは夫まかせなの」
というママさんも多いようです。
そこで、ゲーマー(ゲームを好んでする人)であるちょっと変わったゲーママ(※)から
ママに知ってほしいゲームのあれこれをお伝えしていきます。
ゲームにも制限がある!
以前、あるママから
「息子がほしいっていうから、◯◯っていうゲームを誕生日に買った」と聞きました。
その時、私は「え?」と思いました。
なぜかというと
そのゲームソフトがR指定のものだったからです。
R指定・・・
DVDなどにはありますから、名前くらいは聞いたことがあるかもしれませんが
ゲームにもあるということを知らないという方も多いようなのです。
R指定とは、「年齢制限」です。
「R18」と言えば、18歳以上が観覧できる。というものです。
アダルトはもちろん、残虐なシーンがあるものなどには必ずと言っていいほどR指定がかかっています。
最近では、いじめ描写がある場合もR12などがつくケースもあります。
ゲームでも同様に、R指定が存在します。
最近のゲームは、昔のポリゴンタイプのような平和的なものばかりでなく・・・
その技術の向上ゆえに、描写が美しくなり、リアル感がはんぱありません。
さて。
前述のケース・・・
そのママさん、息子くんがほしいと言ったゲームソフトを何の疑いもなく買ってあげました。
それはR15のゲームソフトでした。
実は、そのソフト、我が家の息子もほしいと言いました。
だから知っていました。
当時、中学生。
今回、知らないで買ったママさんの息子くんも中学生です。
「それ、R指定のゲームだけど、知ってた?」
と聞いたら、
「ええええ!?なんか、えっちなものなの????」と、それはそれは驚愕していました。
いえいえ違います(笑)
そのゲームソフトがなぜR15かというと・・・
それは、「暴力的表現」とみなされているからです。
微量であっても、血が出ます(^_^;)
生き物を殺すシーンがあります(^_^;)
それらが理由のようです。
日本のゲームは基準がある
日本のゲームはCERO(セロ)・・特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構により年齢制限を定めています。
A・・・全年齢
B・・・12歳以上対象
C・・・15歳以上対象
D・・・17歳以上対象
Z・・・18歳以上のみ対象
と5段階に分かれています。
それぞれのゲームソフトのパッケージにこのようなマークが記載されているはずです。
↓ ↓ ↓

※画像は CEROのサイトよりお借りしてきました
案外、細かく分かれているなあ・・と思いませんか。
みなさんのご家庭にあるゲームソフトも見てみてください。
年齢にあったソフトを購入していますか?
では・・・
来年3月に12歳になるお子さんがいたとします。
今年のクリスマスプレゼントに、R12のゲームソフトがほしいと言ったら?
みなさんならどうしますか?
実はこれは、年齢制限に違反したからといって罰則があるかというとそういう問題でもありません。
私なら、R12であることの理由を子どもと話し合い、お互いが納得できるなら買ってあげてもいいかなと思います。
ですが、そもそもこの制度を知らなかったり、ゲーム自体に親が興味がなければ考えもしないのではないでしょうか。
たまたま、我が家は、母親である私がゲーママのため、ルールが徹底していたのかもしれません。
ですが、そんな私だからこそ、声を大にして言いたい。
ゲームは悪くないっっ!!
あ、そうじゃなくて・・・
もっと子どもが興味を持つことに興味を持ちましょう!!
です(^^)
これは、ゲームに限らず、親子関係全般で言えることだと思います。
次回は、今回の話で出てきました「R15のゲームを息子が欲しがった時」の我が家のやりとりをご紹介します。
※ゲーママ・・・ゲーマーとママを合わせた造語

この記事を書いた人 大口 知子

フリーライター・簡単レシピ研究家
夫、大学生・高校生の息子二人
ゆめサポママ@ながの代表メンバーの一人。文章を書く仕事の傍ら、ブログに掲載していた手抜きに見えない手抜きレシピがきっかけでTV出演することに。
SBCテレビ「3時は!ららら♪」NHK長野放送局「ひるとく」などを経て、現在テレビ信州「ゆうがたGet!」木曜レギュラー出演中。
本業ではライティングスクールで後輩の指導にも注力。
http://pianpiano.naganoblog.jp