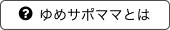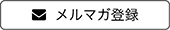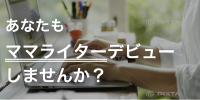子育てサポート
2016.9.3
手のかかる子の子育てをシンプルに楽しむ
「違っている」は「劣っている」ではない

子育てに手遅れはありません
子育てをしていると
「うちの子だけちょっと違うかも」と感じたり、
健診時に保健師から声をかけられたり、
園や学校の先生から病院の受診を勧められた方もいると思います。
それまで子どもの個性や性格だと思って育ててきたのに、
急に「発達障害では」とか「支援が必要」と言われたら
不安や戸惑いを感じます。
「手遅れなのでは」と悲観して相談される方もいます。
発達障害は生まれつき脳の機能障害と言われています。
早期療育が大切だと言われていますが、
子育てに手遅れはありません。
分かったときがスタートです。
頭の中のことは目に見えないのでとてもわかりにくいです。
詳しい説明はこちらが参考になります。
国立障害者リハビリテーションセンター・発達障害情報・支援センター
http://www.rehab.go.jp/ddis/
発達障害と診断されて12年
我が家の息子は3歳の時に発達障害と診断されました。
それから12年間育てて思ったのは、
発達障害は発達しない障害ではなく
発達にかたより(凸凹)がある
ということです。
同学年の子どもよりできないことは多くても、
できるようになる時は必ず来ます。
3歳の時には言葉が話せなかった息子ですが、
今では一日中、何か喋っています。
人前で発言することもできるようになりました。
手のかかる困った子は、困っている子なのです。
お子さんが子育てに「困った」と感じたときはお子さんも困っています。
そんなときは「この子は何に困っているのだろう?」と考えるタイミングです。
何に困っているのかを知らないとお子さんに寄り添った支援につながりません。
例えば、部屋の掃除を指示する場合に「片付けて」と
1回言うだけでできる子がいれば、
5回くらい言ってやっと動き出す子もいます。
「床の上の本を本棚に戻して」と具体的に指示すればできる子、
きれいな部屋の状態の写真を見せて「これと同じにして」と言われればできる子など、
その子に合った伝え方があります。
お子さんに伝わる伝え方を見つけるためには
本人が何に困っているのかを知ることが大事になります。
子供が困っている点をみつけ、
どうすればうまくいくかをみつける
性格と障害の境界線をつけることは非常に難しいです。
十人いれば十通りの特徴があるといわれています。
似たようなことで困っていても全く同じ子はいません。
診断名も12年前は発達障害でしたが、
いまは自閉症スペクトラム(連続体)となりました。
見た目では分からないので周囲への説明が難しく、
親の躾のせいにされることもあります。
子どもの言動が理解できず、ただのわがままにみえてイライラするときもあります。
親は子どもの障害を受容するのが当たり前だと思っていた時期がありました。
ですが、障害受容はそう簡単なことではありません。
将来を考えると不安にもなります。
大切なのは障害を受容することではなく、
子ども本人が何に困っていて、
どうやればうまくいくのかを見つけることです。
人と違うことは劣っていることではありません!
次回は、発達がデコボコしている子どもとの子育てライフをシンプルに楽しめて
「なんとかなるかも」と思えるような具体的な日常生活のコツをお伝えします。

この記事を書いた人
花石しまりー:デコボコライフアドバイザー
http://symary.naganoblog.jp/
長男(2001年生)が3歳の時に発達障害(自閉症スペクトラム)と診断されてから育児書通りにはいかない子育てをブログに連載。個別相談や講演、発達障害の啓発活動に取り組んでいる。子どもの発達が気になる親の会こもれび代表。